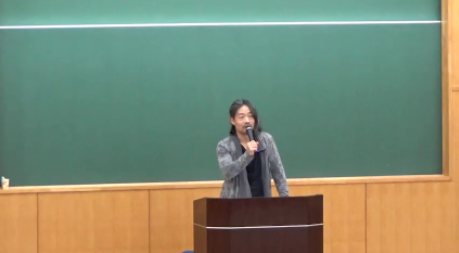2025年10月9日(木)〜2025年12月18日(木)
芭蕉と『おくのほそ道』の旅 旅は道連れ世は情け
芭蕉は46歳の元禄二年(1689)3月27日に陸奥の旅に発ち、大垣に到着するまで156日その行程は2500キロに及ぶものでした。私たちが脳裏に浮かべる芭蕉と曽良は、日々早朝から日没まで歩き続け風雨や灼熱に晒されて苦しむ姿です。5年前の『野ざらし紀行』で名古屋にたどり着いた身なりは「笠は長旅の雨に破れ紙子はよれよれになり、みすぼらしい姿は自らが見ても哀れ」だったと記しています。
『おくのほそ道』の旅の一コマを『曽良旅日記』によって見ましょう。
1)黒羽・須賀川からは馬で送られたこと。
2)白河の関越えを故事に倣って黒羽で小袖と羽織を預かったこと。
3)仙台領の矢本新田で喉が渇き家ごとに湯を求めたこと。
4)堺田から市野々まで屈強な若者に荷物を持たせて山刀伐峠を越えたこと。
5)尾花沢・山寺間で馬を借り、鶴岡を発つ時に羽黒の会覚阿闍梨から旅行用の帳面と浴衣が届けられたこと。
6)吹浦では思い掛けず旧知の美濃の商人弥三郎(俳号低耳)に出会い、入善・黒部間では人を雇って荷物を持たせたこと。
本文には見られない場面が『旅日記』によって窺い知られます。これらに焦点をあてつつ実地踏査の体験を踏まえて旅の真実にせまります。
- 開催日
-
備考
なし
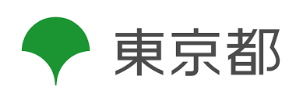

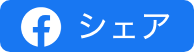
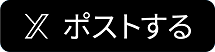





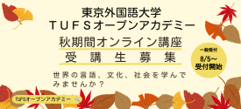


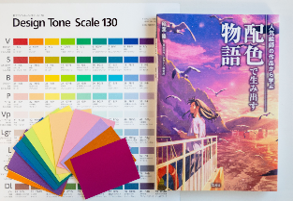




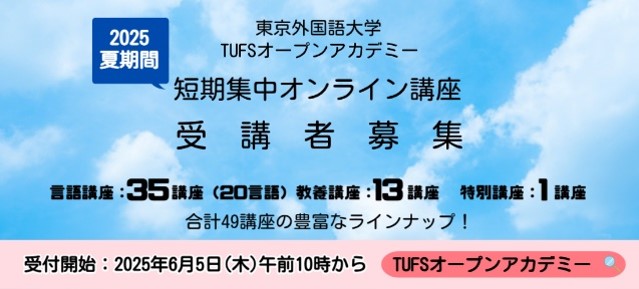
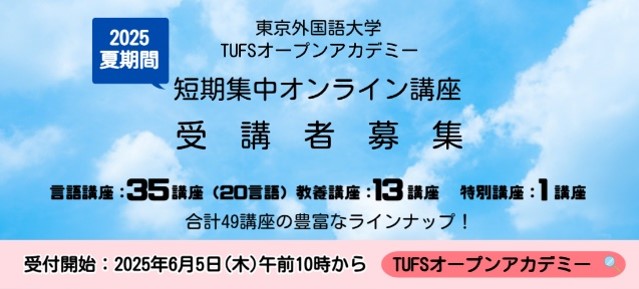
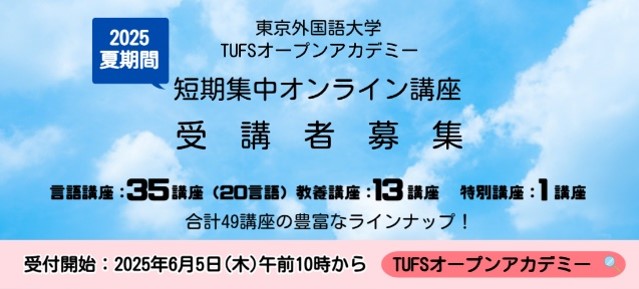
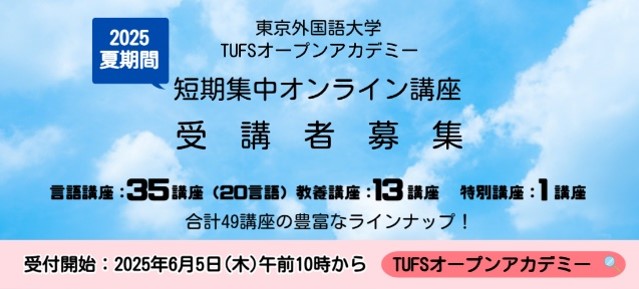
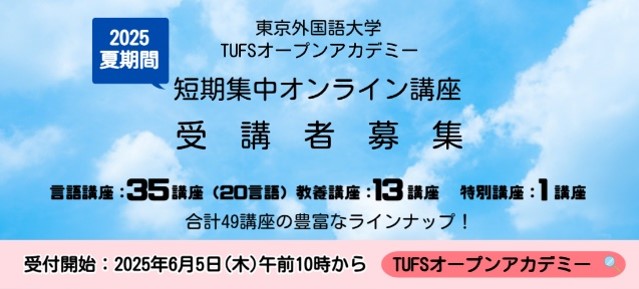
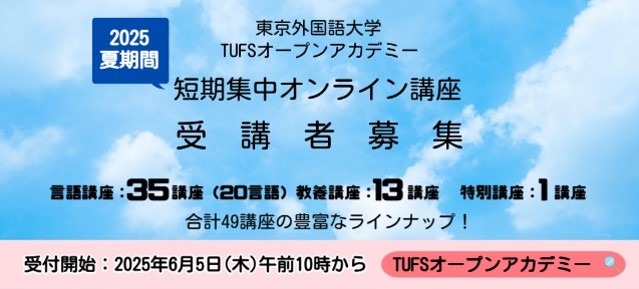
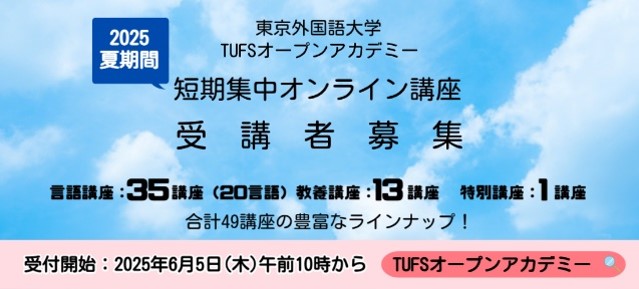
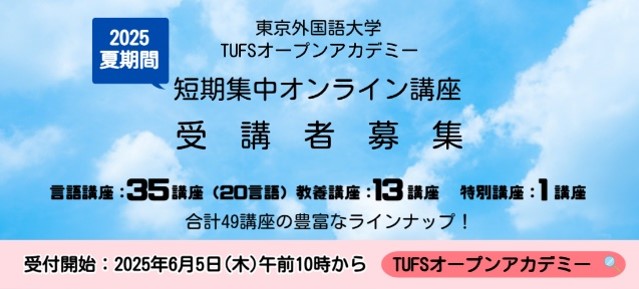
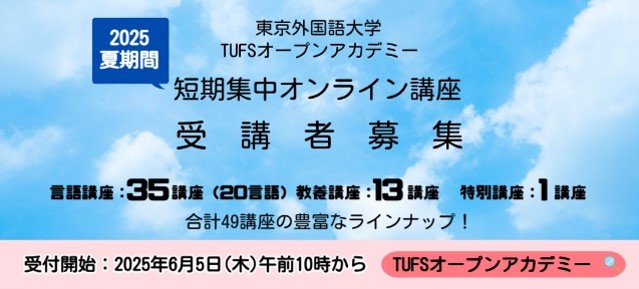
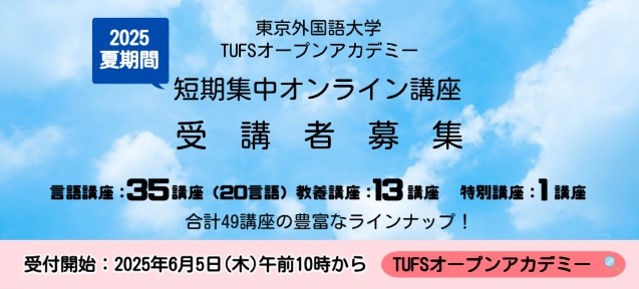
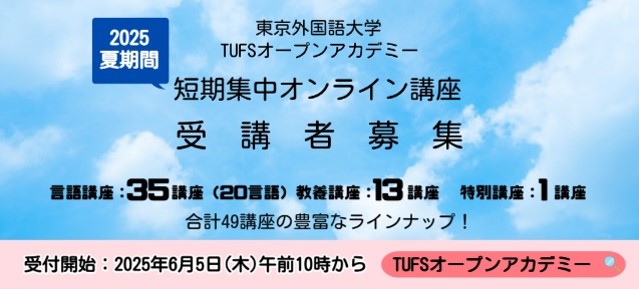
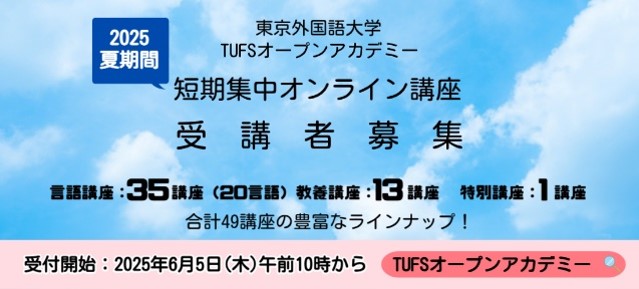
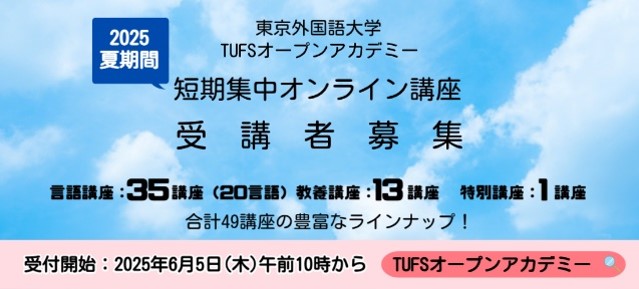



.png)
































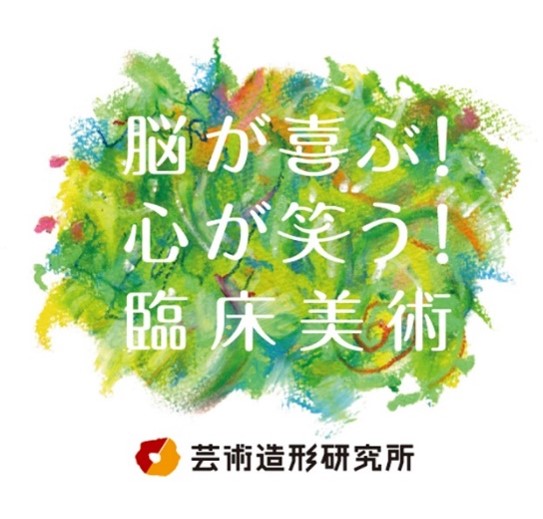
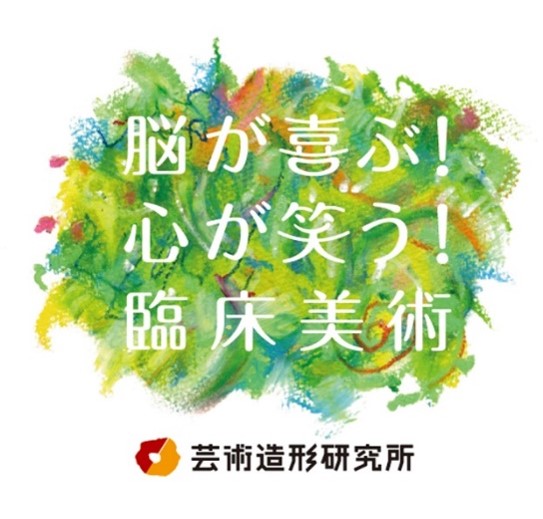
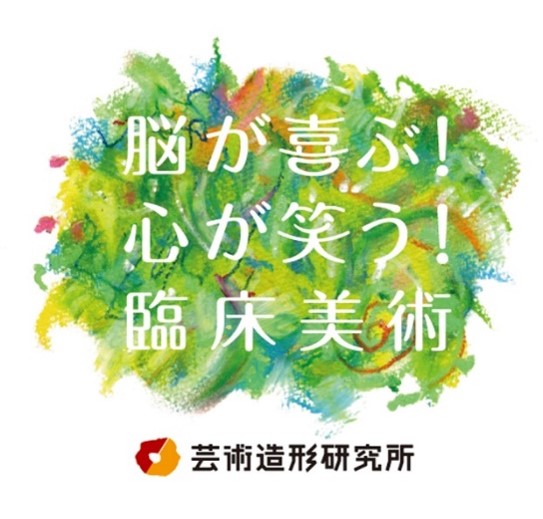
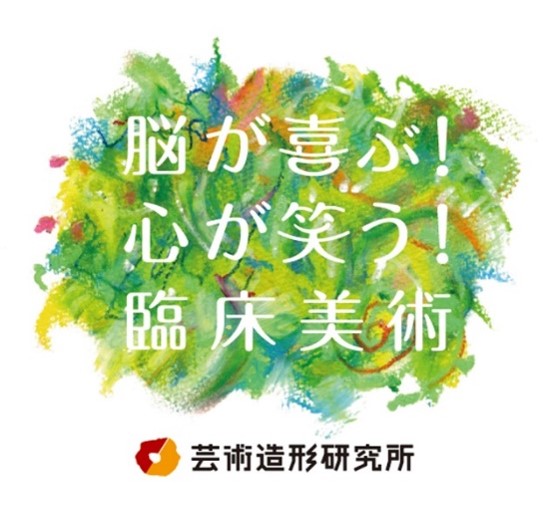

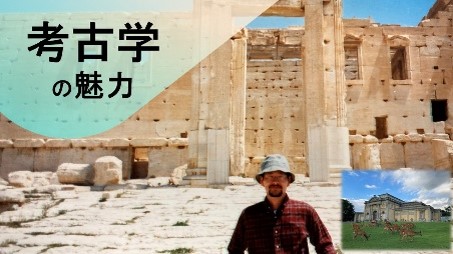


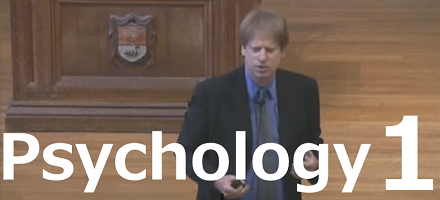
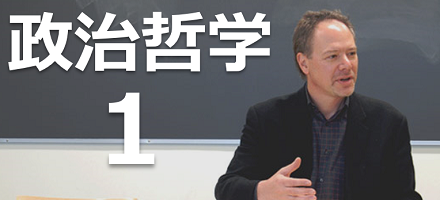



からわかること.png)
が語るオーストラリアの自然と文化.png)


.png)
.png)

.png)

.png)