2025年10月25日(土)〜2025年11月1日(土)
租税法入門
1 「税とは何か」を沿革から学びましょう。
・わが国の租税は、律令制度における租・庸・調に始まり、近世まで、主に穀物(租=米)によって納税されていました。
・明治以降では、地租改正条例によって土地や家屋に対して課税されたり、所得税が導入されたり、さらには、戦費調達として、所得税の源泉徴収制度や法人税が創設されました。
・第二次世界大戦後においては、シャープ勧告により、所得税などの直接税と申告納税制度が創設され、現在では、消費税の創設(平成元年)によって、税の類型は、所得課税、消費課税及び資産課税等に分類されています。
2 「税についての基本的考え方」を学びましょう。
・世界に目を転じれば、イギリスのマグナカルタに始まり、アメリカのボストン茶会事件やフランス革命を経て、現在のような「租税法律主義」の考え方が定着しました。
・租税法律主義に加えて租税公平主義及び徴収確保主義が「租税の三大原則」とされていますが、租税法律主義とは、行政権による恣意的課税から国民を守るためにあり、そのうちの中心的考え方である「課税要件」とは何かを理解しましょう。
3 「税の種類とその性格」を学んでみましょう。
・所得課税、消費課税及び資産課税等に分類されるわが国の租税について、その代表的な所得税、消費税及び固定資産税の課税の仕組み(骨格)とその性格を学んでみましょう。
4 「税額の計算」をしてみましょう。
・税額計算の根拠となる「収入」と「必要経費」、「所得」の意味・内容を理解しましょう。
・税額計算の基礎となる「所得」(=収入-経費)は、足し算と引き算で計算されます。
「税額」は、主に掛け算による面積計算で求められます。
→ 税額計算は決して難しくありません。
- 開催日
-
備考
なし
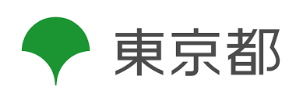

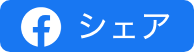
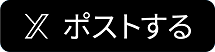

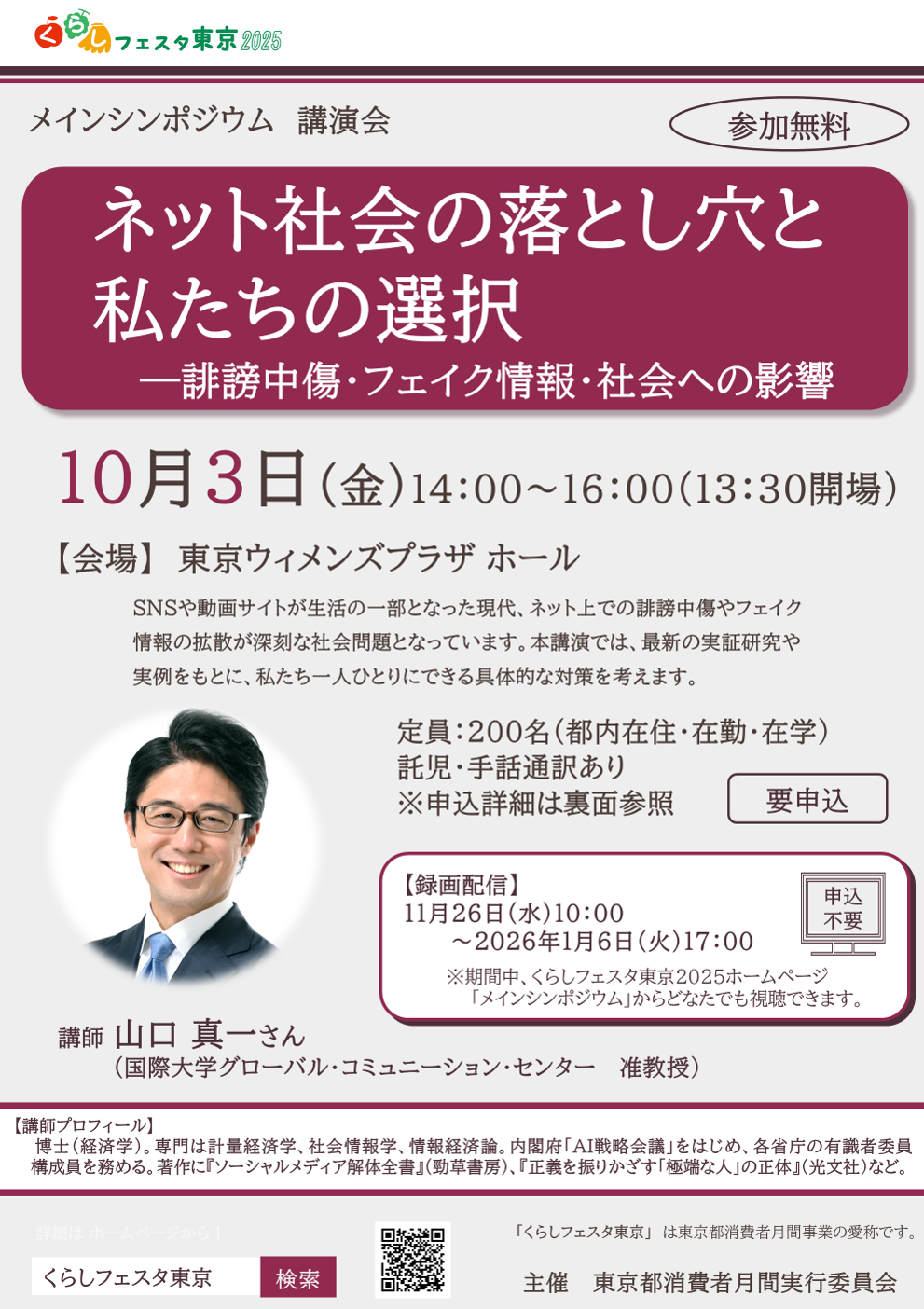
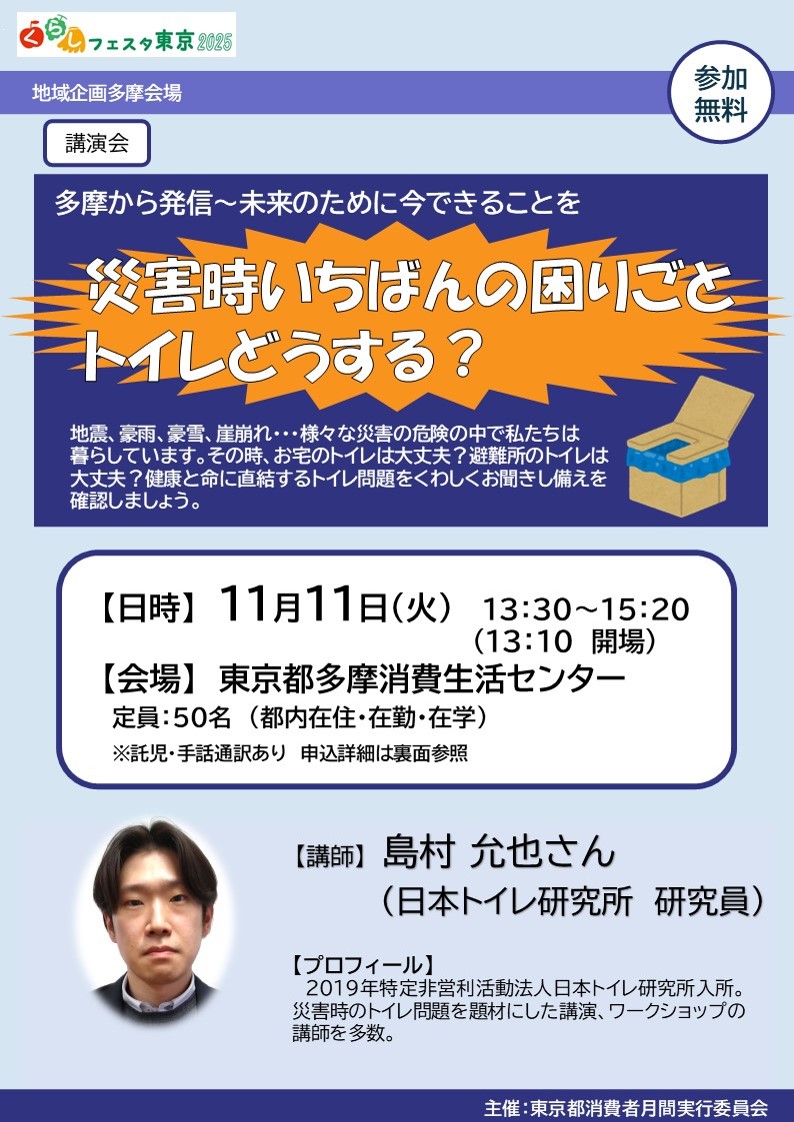

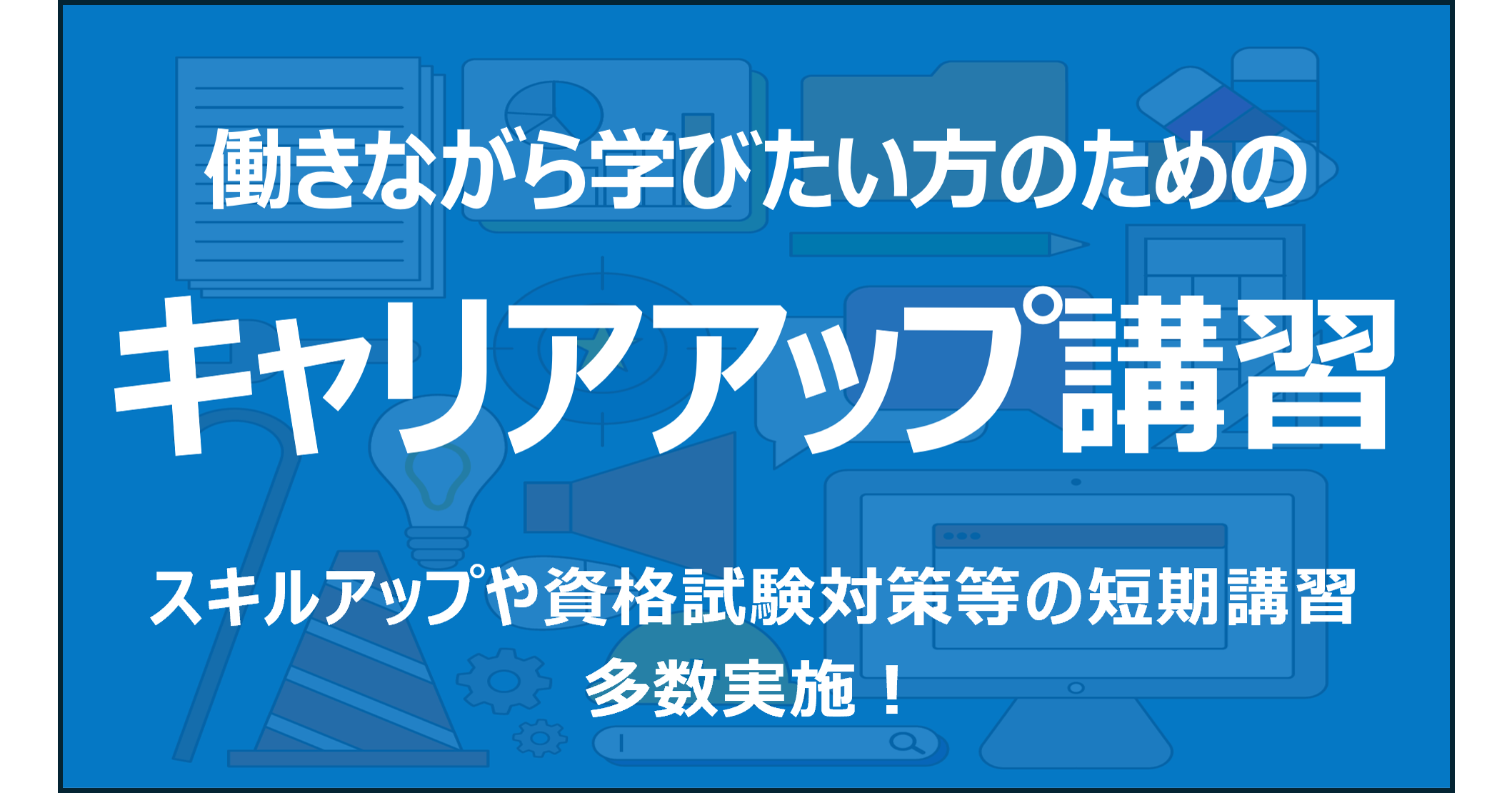
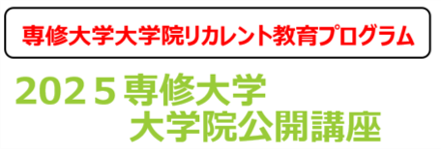
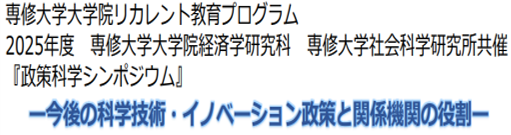
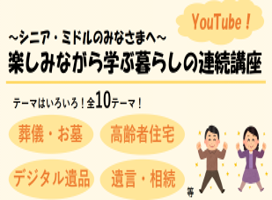
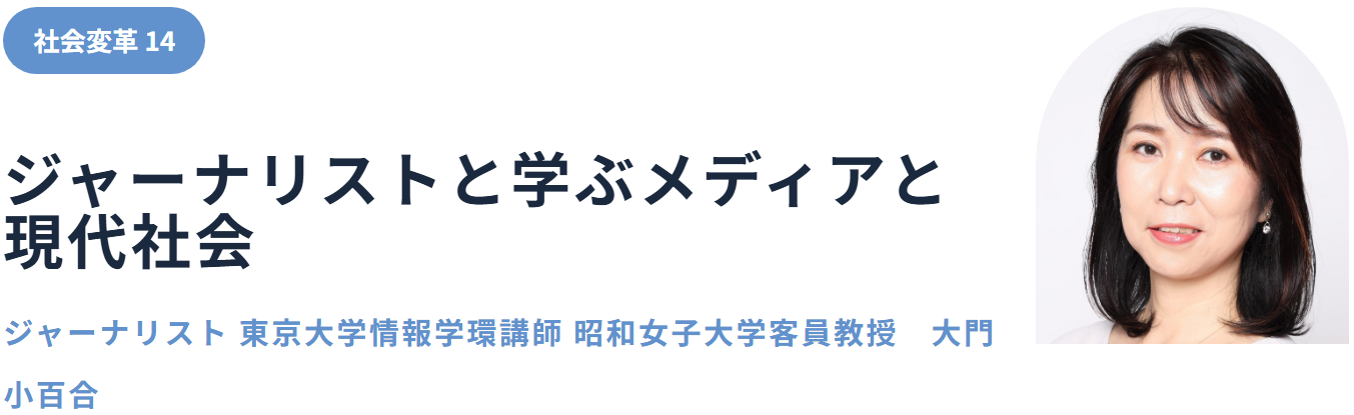
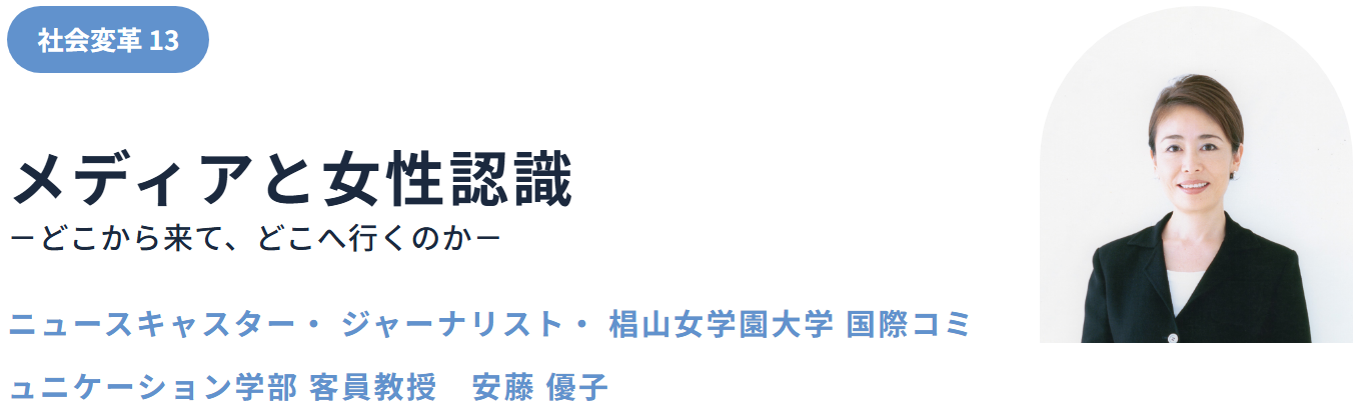
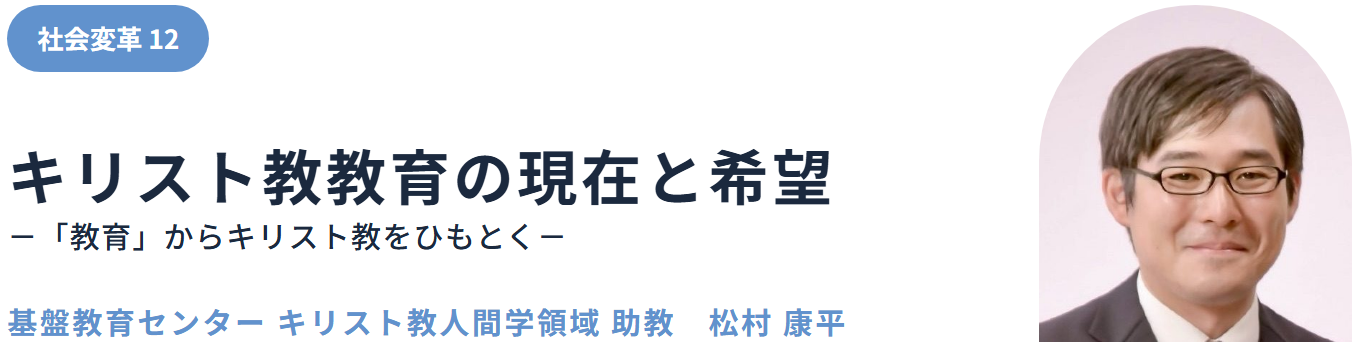
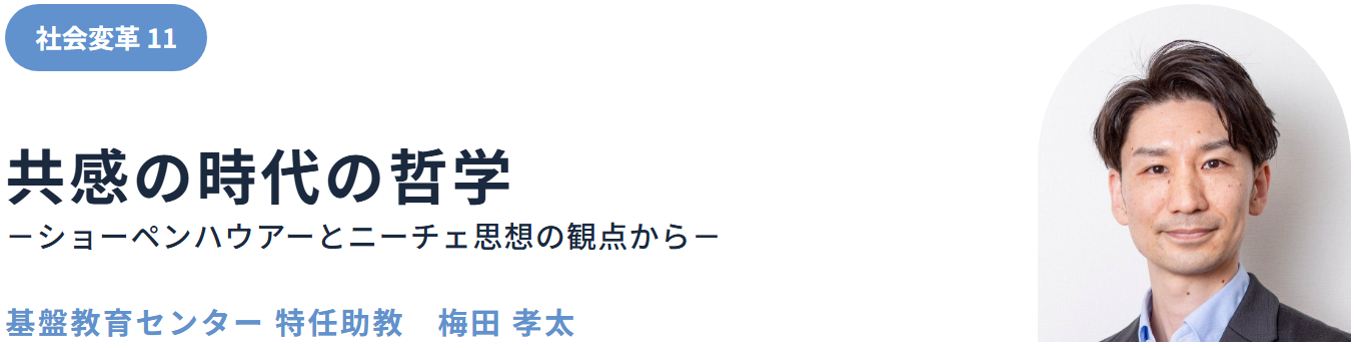
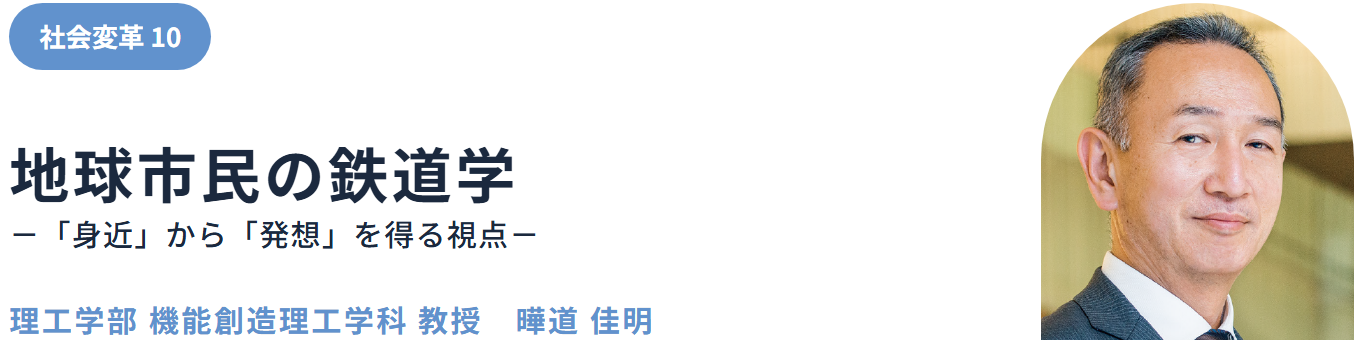
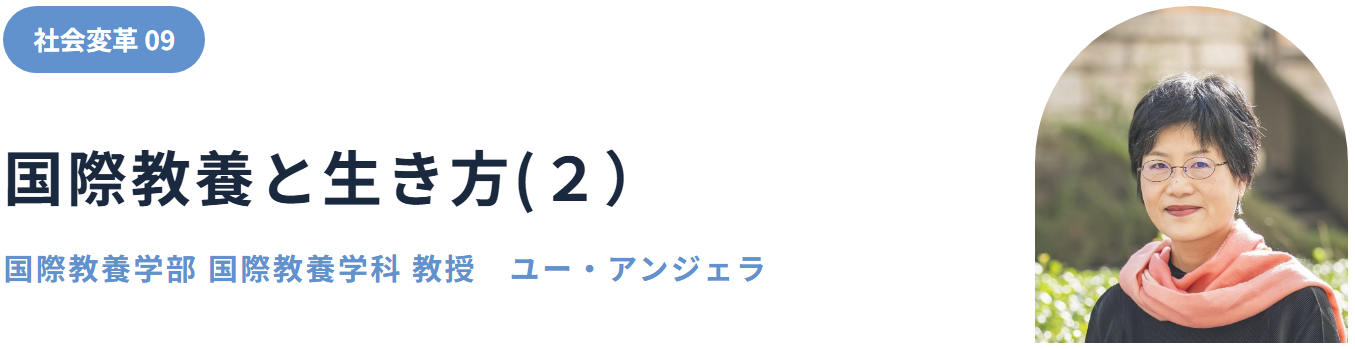
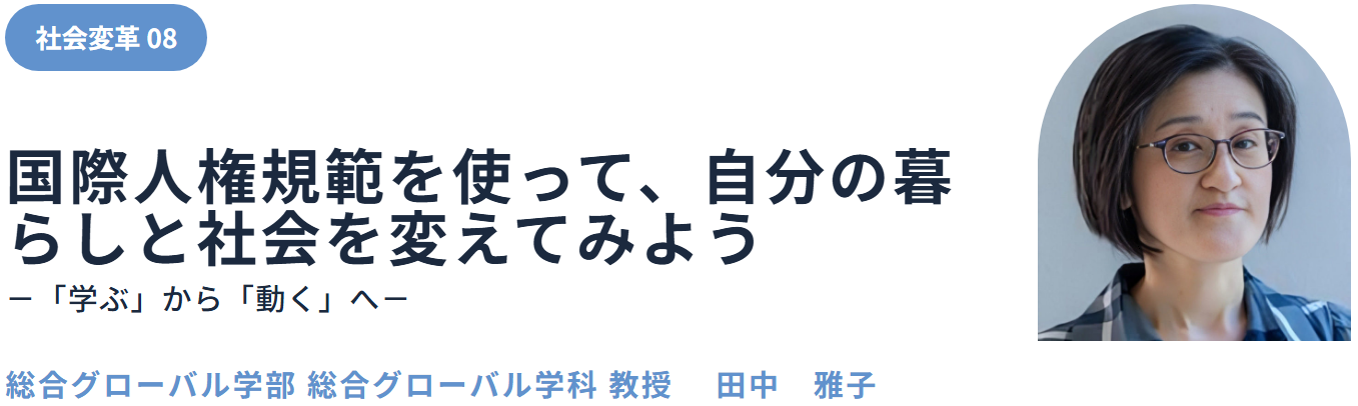
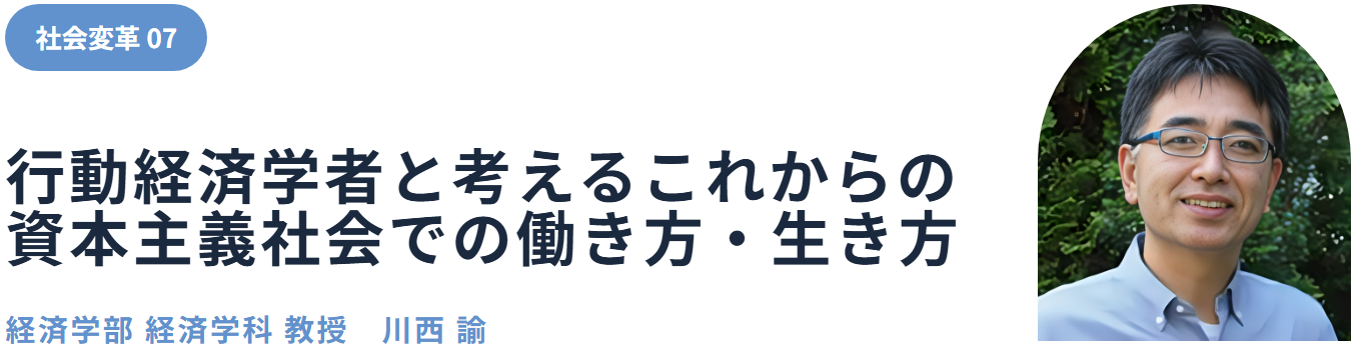


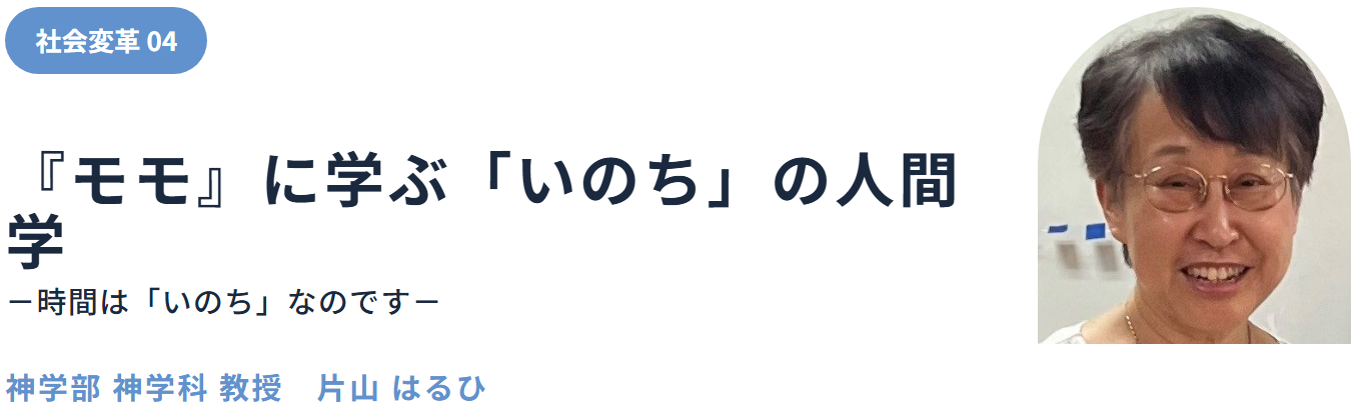
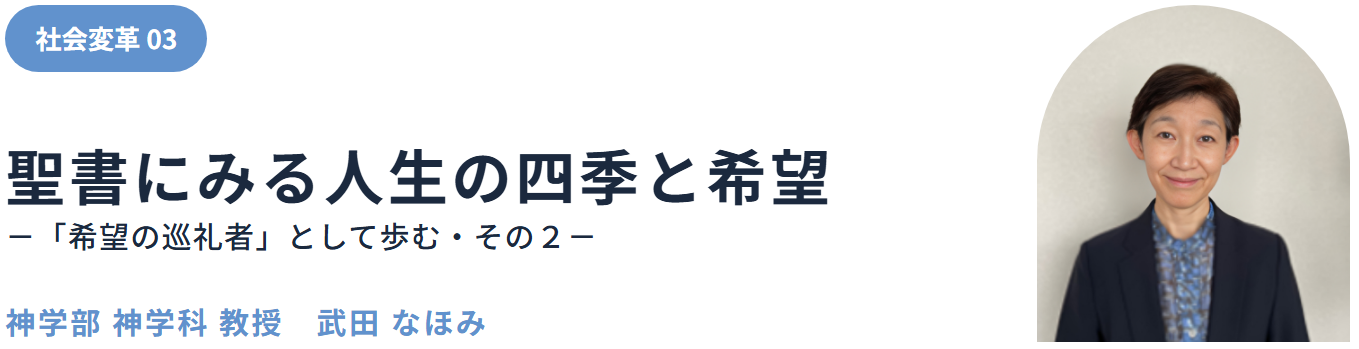

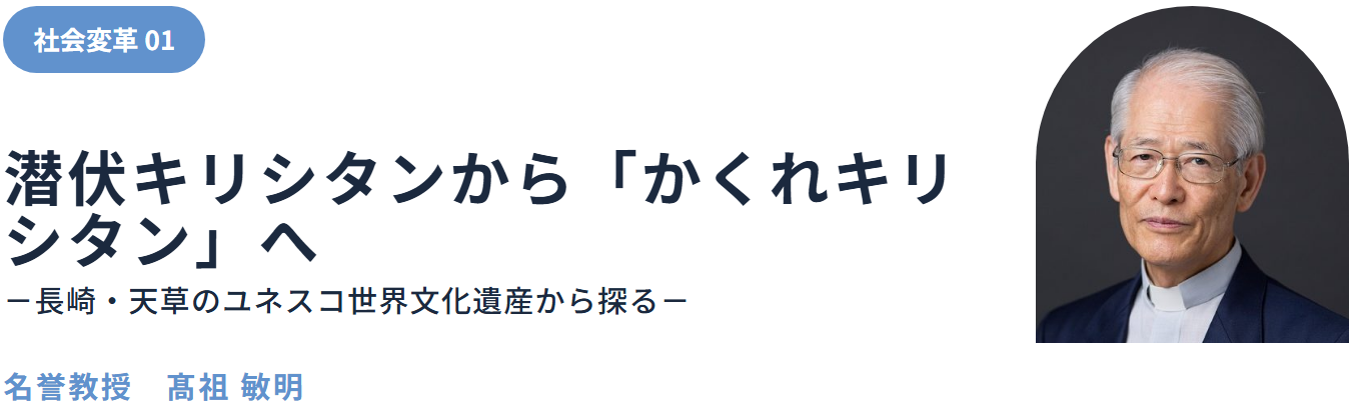
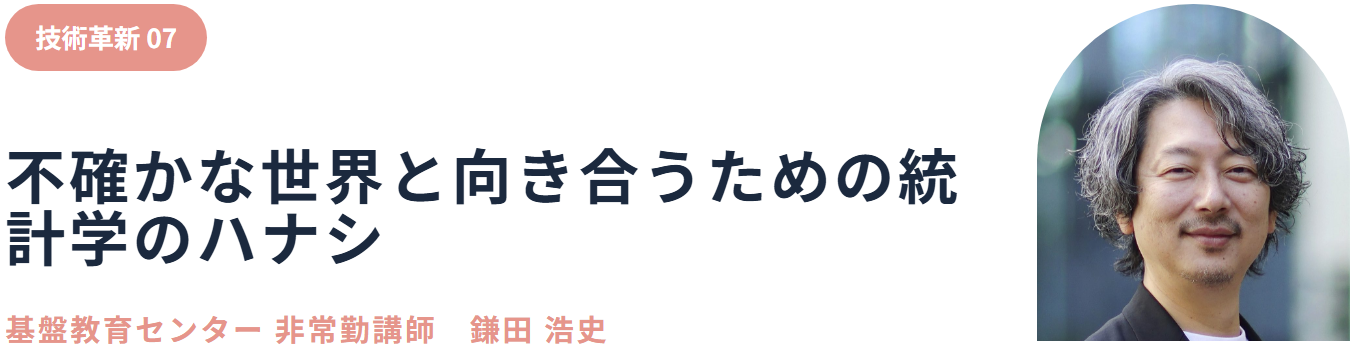
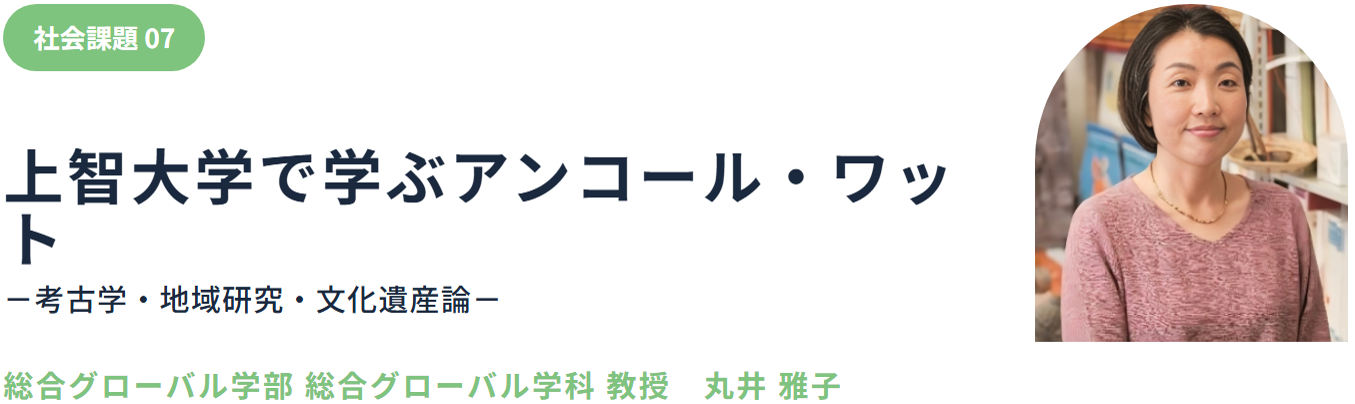

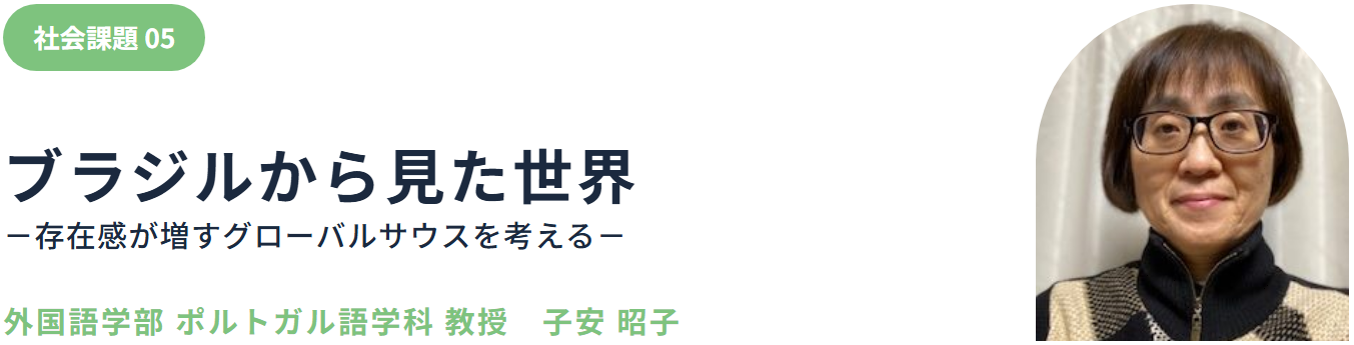
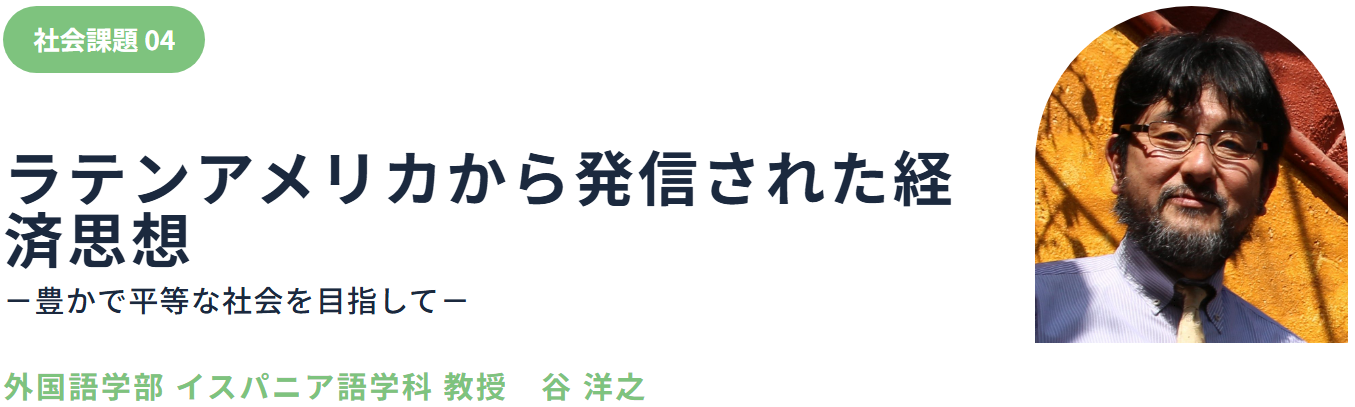
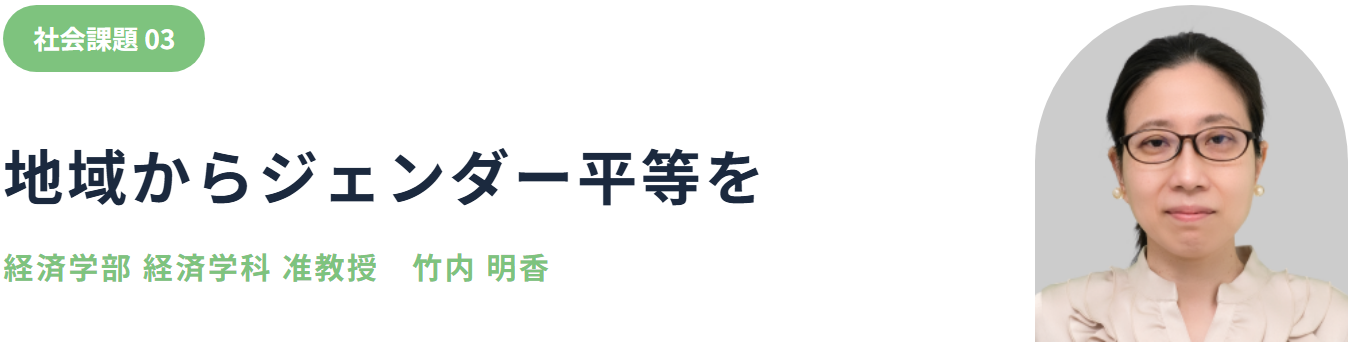
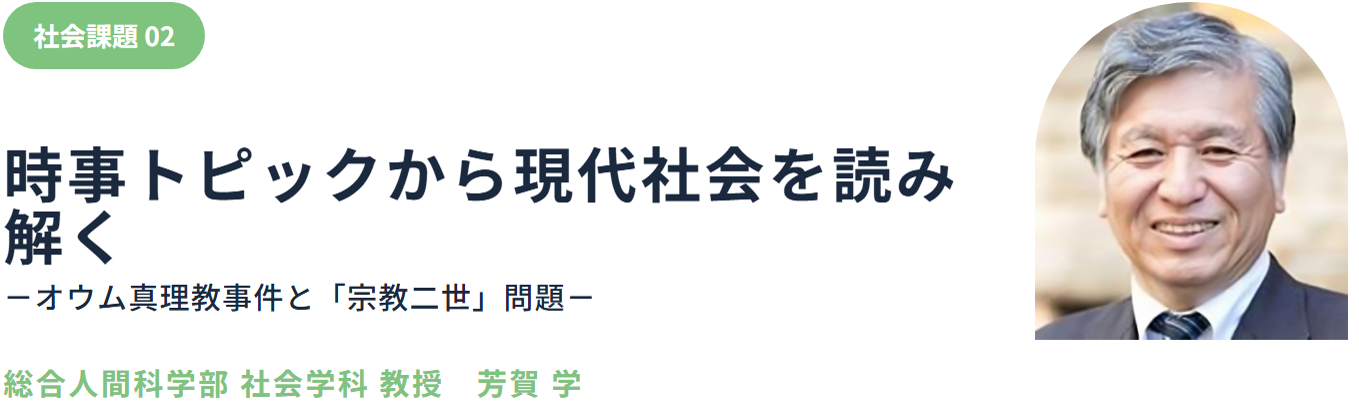
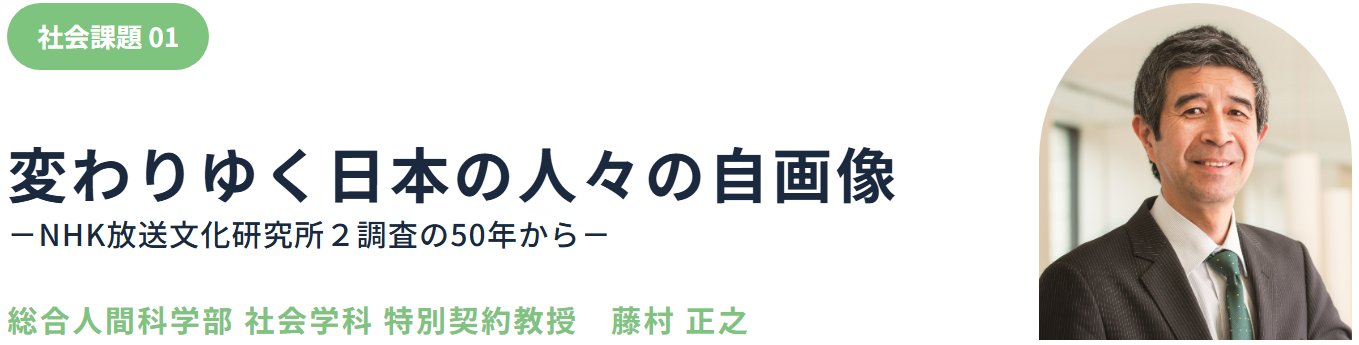
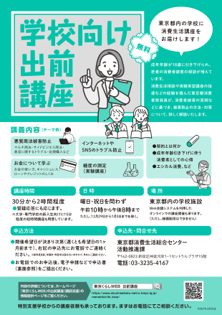



.png)

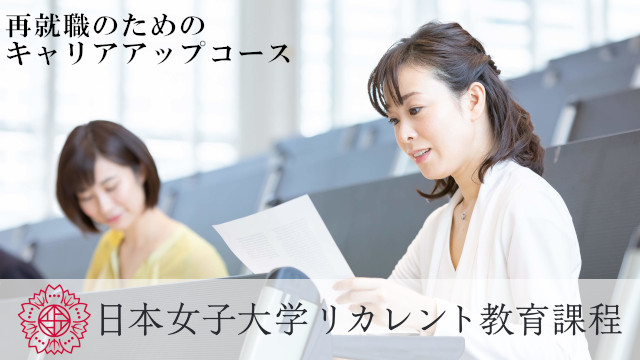
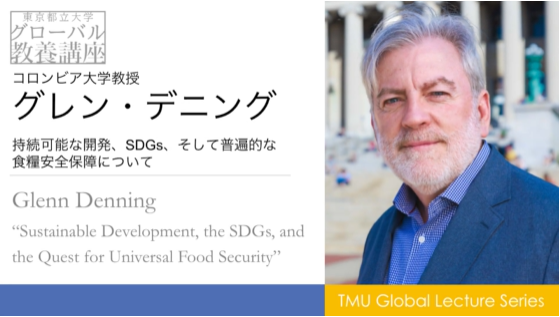
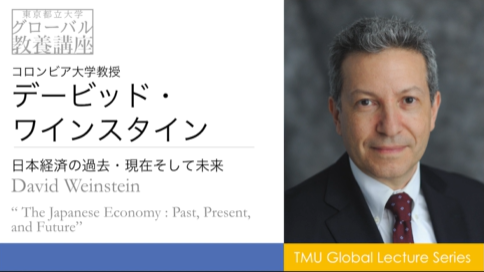

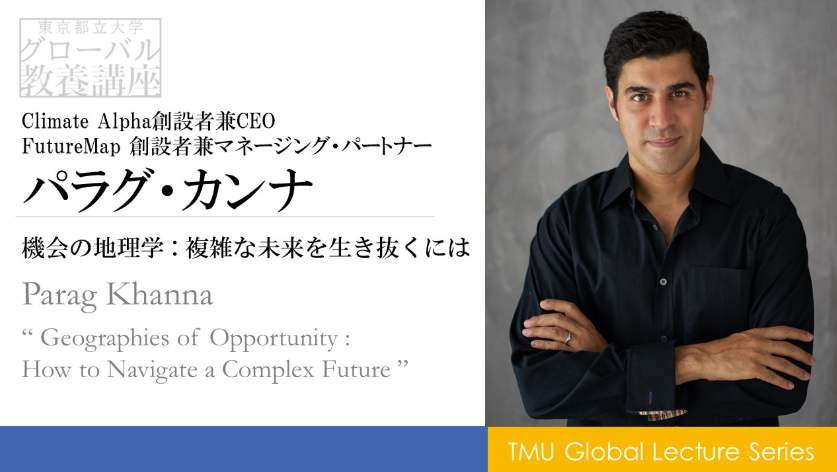

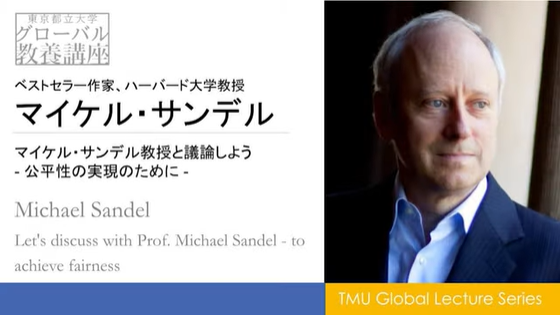
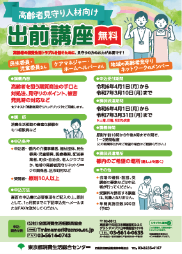
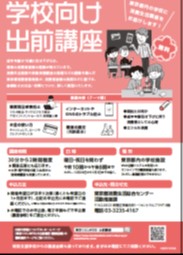


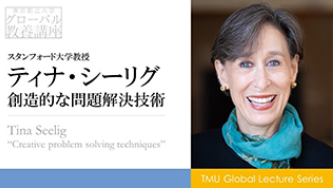

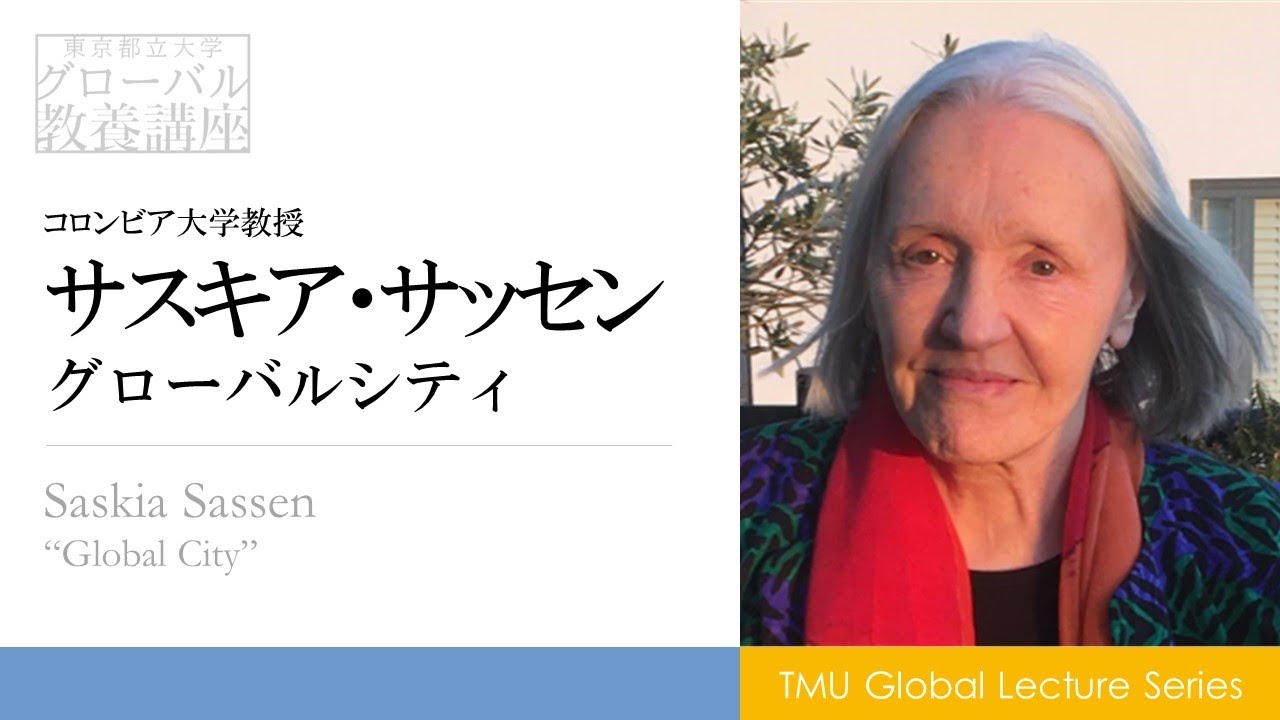
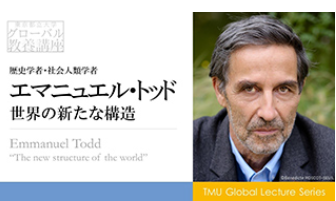


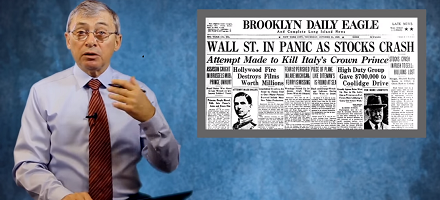




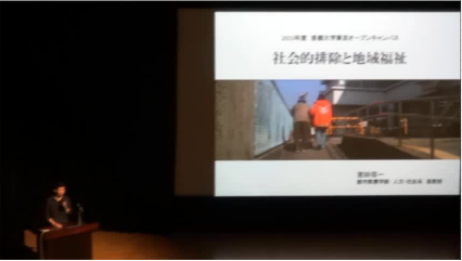
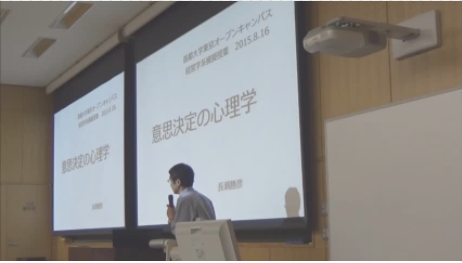

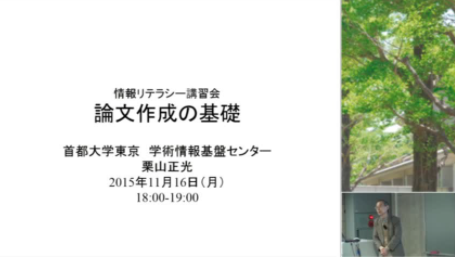


によるフードデザート問題の分析.png)
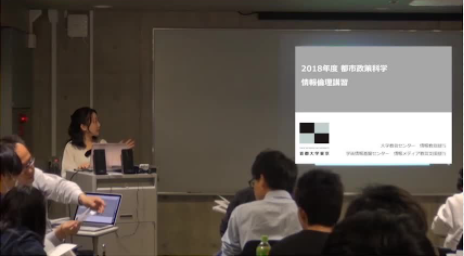
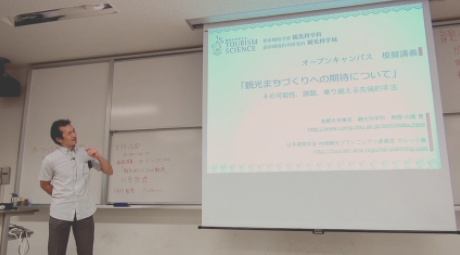



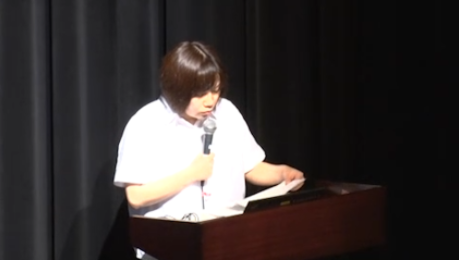

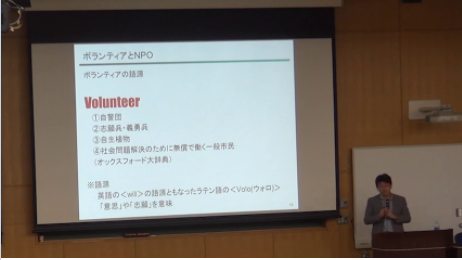
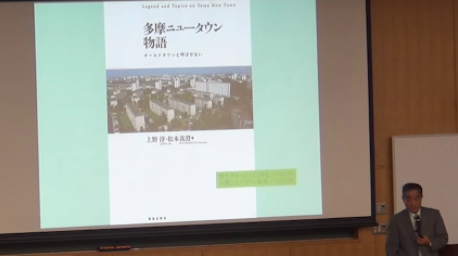


.png)
.png)