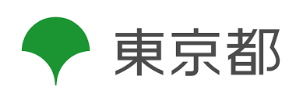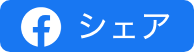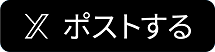【オンライン】『劇的』に楽しむシェイクスピア 小泉八雲と妻・セツ

シェイクスピア講座でなぜ小泉八雲?と疑問に思われる方も多いでしょう。
小泉八雲ことLafcadio Hearnは「怪談」の作者として有名ですが、「怪談」の中にシェイクスピアからの引用があることはあまり知られていないようです。なぜかと言うと、多くの日本人は翻訳された「怪談」を読んでいるからだと思われます。つまり、小泉八雲は全ての作品を英語で発表し、西洋の読者のために書いていました。さらに、八雲は日本の大学で教鞭を取り、シェイクスピアを好んで教えていました。ということで、昨年に続いて今年も本講座で小泉八雲を取り上げます。そのポイントは二つ。
(1)小泉八雲から学ぶ「防災」~A Living God
Tsunami(津波)が英語として使われるようになったのは、小泉八雲のA Living Godが広く読まれたからと言われています。本作品から「稲むらの火」が生まれ、World Tsunami Awareness Day(世界津波の日)制定までの過程を追いながら、八雲文学から「防災」について読み解いていきます。
(2)妻セツの語りから生まれた八雲の再話文学
八雲とセツは日本語でどのようにコミュニケーションを取っていたのでしょうか?それを知る手がかりは、八雲がセツに宛てた手紙文(下の写真)にあります。
この手紙文の始まりは
「小 ママ スタシオンニ タクサン マツノ トキ アリマシタ ナイ」
そして終わりの文章は
「五ジ イマ オトキチサン アリマス」
この独特の日本語は「ヘルンさん言葉」と呼ばれ、その根底には幕末に横浜在住のイギリス人が書いたExercises in the Yokohama Dialect(横浜方言演習)があります。それは「Pigin(ピジン)日本語」とも呼ばれ、開港地での重要な商業取引きの手段として役に立った「方言」でした。ここに着目すると、明治初期にシェイクスピアの有名なセリフが、次のように訳されていた謎が解けます。
To be or not to be、 that is the question.
アリマス アリマセン、アレワ ナンデスカ
明治7年(1874)発行 The Japan Punch 1月号より
- 開催日
-